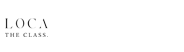サウナブーム終焉?サウナに「選択肢」をもたらしたブームの今後
 サウナコラム
サウナコラム先日、とある記事に「サウナブームが終焉に向かっている」と書かれているのを発見しました。一時期はかなり盛り上がりを見せたサウナ業界も、閉店を余儀なくされるお店が出てきたり、ブームの影響で常連客が離れてしまったりと、課題も多いとか。「サウナ人口が減っている」ということも書かれており、素直に「これからのサウナ業界はどうなっていくのかな」と考えさせられました。そこで、今回はサウナブームの歴史をたどりながら今後のサウナ業界について考えたいと思います。
- 目次
1.そもそも「サウナブーム」はなぜ起きた?
ドラマサ道の影響

ドラマの放送により「サウナの楽しみ方」がわかりやすく広まりました。サウナの入り方から、「ととのう」心地よさ、サウナめしの魅力、サウナ友達の魅力などなど……。
映像化されたことで、これまで「サウナ=おじさんが行く場所」というイメージを大きく変えたと言われているんですよね。
ストレス社会とマッチ

サウナがここまで広まったのは、ストレス社会を生きる現代人の”癒しの場”になったからではないかと思われます。
サウナは心身ともに健康を目指せる場所です。「もっと休みたい」「ストレス解消したい」というニーズとサウナ環境がベストマッチしたことが大きいかもしれませんね。
アウトドア&旅行との相性がいい

新型コロナウイルス拡大の時期(2020年以降)には「3密(※)」を避けられるとあってアウトドア、キャンプに注目が集まりましたよね。
こうした背景から「テントサウナ」「アウトドアサウナ」にも注目が集まったこともブームに影響をもたらしているのは出ないでしょうか。
※密室空間・密集場所・密接場面
2.サウナブームによって起きたこと
「空前のサウナブーム」と謳われた2019年。『ユーキャンが発表した流行語大賞』に「ととのう」がノミネートされた2021年。
サウナブームと言われた2019年から早5年が経過し、いまやサウナは「ブーム」ではなく「文化」として根付き始めたという話もよく耳にします。サウナブームから5年経った現在、サウナ業界はどのように変化しているのでしょうか。
・「ととのう」が共通言語へ

「ととのう」という言葉がサウナ未経験の人にまで届いていたり、サウナを頭ごなしに否定する人が減っていたり。サウナに行ったことはないけど【興味が出てきた人】【コアなサウナ情報を知っている人】が増えてきたように思えます。(筆者の肌感ですが)
TV番組、ドラマ、雑誌などでサウナがよく取り上げられるようになったことで以前よりも「サウナの良さ」「サウナの魅力」に触れる機会が増えたからだと考えています。
・サウナ特化型の新店舗がオープン

『渋谷SAUNAS』や赤坂『サウナ東京』、大阪心斎橋『大阪サウナDESSE』など、2022年〜2023年には、サウナをメインに楽しみ『サウナ特化型施設』のオープンが相次ぎました。
豊富なサウナ室、水風呂、ととのいスペースの充実度などが重要視されるサウナ特化型施設。サウナブームにより「湿度の高いサウナが好み」「昭和ストロングスタイルが好み」「水風呂は15度がすき」「サウナ室は黙浴がいい」「おしゃべりしたい」など、多様性が求められる現代だからこそ生まれた、と言えるかもしれません。
・サウナ×旅行業界の勢いがすごい

サウナ目的で旅をする人もめずらしくありません。宿泊先を探す条件のひとつに「サウナがあるか、ないか」と、新しいニーズを求める層が増えてきたように感じます。
新設されたホテルにプライベート付きサウナ付きの客室が新設されたり、コテージや古民家にサウナ付きプランができたりと、「サウナ×ホテル」・「サウナ×旅」・「サウナ×リトリート」などなど、サウナ+αの体験ができる場所を人々が求めているようにも捉えられます。
・混雑を極めるサウナ施設

入場制限が設けられたり、サウナに入るために並んだり。
サウナ人気が高まるにつれて、「混みすぎてリラックスできない」「ルールを守れない人がいて安らげない」など、マイナスな声も多く耳にするようになりました。
一方、こうした声を受けて「待ち時間が発生しないシステム」を導入するサウナ施設ができたり、完全貸切で楽しめるプラベートサウナがオープンしたり。課題解決に動く業界の動きも見て取れます。
・「好きだったけど…」とサウナを去る人も増えた

ブームの影響で「サウナ行くのやめた」という方も多いです。
理由は大きく2つ。混雑などの影響で、以前のような環境でサウナを楽しめなくなったから。「ルール」「マナー」などの決まりが増えて、心から楽しめなくなったから、など。サウナ好きが増える一方で、サウナを去る人も増えていたのは事実です。
ちなみに、一般社団法人日本サウナ・温冷浴総合研究所が発表した『サウナ愛好家人口推移』によれば、サウナブームの2019年以降、サウナ人口は全体として減少の一途をたどっているとか。
3.悪いことだけじゃない。サウナブームは「選択の自由」を生んだ

筆者自身、「サウナブームは悪いことばかりじゃない」と感じています。
サウナの魅力がより広まったことで、サウナに「選択肢」が生まれたなと感じているからです。
・銭湯 ・スーパー銭湯 ・日帰り温浴施設 ・サウナ特化型施設 ・プライベートサウナ ・アウトドアサウナ施設 ・グランピング施設 ・キャンプ場 ・温泉旅館
思いつく限り「サウナが楽しめる場所」をあげてみました。場所が増えたということは、サウナの楽しみ方も広がったと考えられます。

例えば、銭湯サウナ。一般的な銭湯のサウナは、ほかの施設と比べてもコンパクトです。でも、そのコンパクトさが落ち着くし、常連さん同士の会話を盗み聞きするのもたのしい。
サウナ付温泉旅館やアウトドアサウナは、非日常を感じながらサウナに入れますし、サウナ特化型施設では、自分の好みのサウナをガツガツと楽しめる環境がととのっています。

そしてプライベートサウナ。「サウナ待ち」や「休憩待ち」、「黙浴」の必要がない、完全プライベート空間。その分、費用はほかと比べて上がりますが、自分だけのサウナと水風呂、休憩スペースがある安心感は、この上ない贅沢を感じられるポイントですよね。

どのサウナにも、それぞれの良さがあります。
地元のひとたちに混ざって懐かしい銭湯空間に浸りたいのか、ガツガツサウナを楽しみたいのか、非日常感を感じたいのか、誰にも邪魔されない環境でサウナを楽しむのか……。
楽しみ方の選択肢、自分にあったサウナを選べる選択肢が増えたのも、サウナブームがあったからこそだと思っています。
4.サウナブームの今後。これからもサウナを楽しみたい!

現在のサウナ業界をみていくと、より多様性を求められる時代になったと感じます。
正直、今後のサウナ業界がどう変わっていくかは分かりません。
ですが、多様なニーズに応えようと奮闘する人たちがいる限り、ブームが落ち着いてもなお、想像もしていなかったようなサウナの可能性を見せてくれるのでは、と思っています。
筆者はライターとしてサウナ業界に関わっていますが、サウナに携わる方々は総じて、”利用者想い”です。「もっと喜んでもらいたい」「サウナで日頃の疲れを癒してほしい」と利用者に向き合い、本気で事業に取り組んでいる方が多いんですよね!
加熱したブームが落ち着くのは、どの業界でもよくある現象です。業界ならではの課題もあると思いますが、わたし自身はこれからも引き続き、サウナ愛を深めていきたいと思っています!